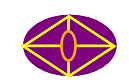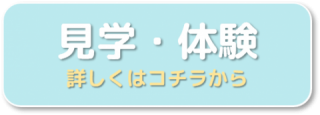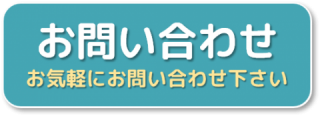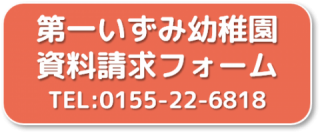園長通信
園長先生からのメッセージ
11.テレビが子供の脳を壊す
2010-04-07
実は前回TVについてお話しましたが、7月15日付の週刊アエラに、上記のタイトルのようなショッキングな記事がタイムリーにのっていました。
見られた方もいると思いますが、その中でカラーテレビとともに育ったテレビ第一世代が親になり、つけっぱなしにしても何も違和感がない状況。
そして今では、その視聴の対象はビデオやテレビゲームなどの普及が、長時間視聴に拍車をかけているということです。
見られた方もいると思いますが、その中でカラーテレビとともに育ったテレビ第一世代が親になり、つけっぱなしにしても何も違和感がない状況。
そして今では、その視聴の対象はビデオやテレビゲームなどの普及が、長時間視聴に拍車をかけているということです。
2歳6ヶ月のA君は11ヶ月で歩き、語彙数も豊富であった。しかしその後、教師の母親が職場に復帰、祖母に預けられた半年で、A君から言葉が消えた。返事もしなければ、家族とも目を合わせない。そして一人遊びが増え、たびたび暴れるようになった。
A君を調べてみると、テレビを見る時間が急増。一日に見る時間はアンパンマンのビデオにはじまり、一日8時間にもなっていたということです。
言葉の遅れは先天的な要因だと考えられていましたが、いまテレビ、ビデオ付けの生活で「新しいタイプの言葉遅れ」が増えているそうです。
A君を調べてみると、テレビを見る時間が急増。一日に見る時間はアンパンマンのビデオにはじまり、一日8時間にもなっていたということです。
言葉の遅れは先天的な要因だと考えられていましたが、いまテレビ、ビデオ付けの生活で「新しいタイプの言葉遅れ」が増えているそうです。
こうした子はおとなしく、手がかからない一見いい子であるが、言葉が遅れると、自分の意思を伝えたり、聞いて判断するという「考える力」が育たなくなります。
4歳、5歳までこのままだったら、言葉や考える力を完全に取り戻すことは非常に難しくなります。
4歳、5歳までこのままだったら、言葉や考える力を完全に取り戻すことは非常に難しくなります。
ある統計で特に長時間だった子供の行動を観察すると、共通した特徴が「友達関係がもてない」「表情が乏しい」「視線が合わない」「遊びが限られる」「話し言葉に抑揚がない」・・など、特徴の多くは自閉症の子供に似ているそうです。
北大の沢口教授によりますと「ADHD(注意欠陥多動症)の急増などはテレビ付けの環境が影響を及ぼしていると考えざるを得ない。」と言ってます。
沢口教授が危惧しているのは、テレビを子守がわりにすることによって、子供が母親から引き離されることであって、脳の発達に必要な双方向の刺激、つまり母親とのコミュニケーションがとれなくなることだそうです。ほんとに怖いことですね。
沢口教授が危惧しているのは、テレビを子守がわりにすることによって、子供が母親から引き離されることであって、脳の発達に必要な双方向の刺激、つまり母親とのコミュニケーションがとれなくなることだそうです。ほんとに怖いことですね。
今問われているのは「見方」「見せ方」だそうです。
ある地域で月に一度「ノーテレビデー」を1年間続けたら、叩く、蹴るという攻撃的な行動が減って、「やだ」「死ね」という単語でしか話せなかった子が、文章の形で話せるようになったという報告が出ています。
ある地域で月に一度「ノーテレビデー」を1年間続けたら、叩く、蹴るという攻撃的な行動が減って、「やだ」「死ね」という単語でしか話せなかった子が、文章の形で話せるようになったという報告が出ています。
最初はやるのは大変ですが、次第に慣れさせていくと、あっけないほど子供は順応してしまい、一度「退屈する自由」を経験すると、子供たちは初めて自分で自発的に考え、遊び始めるようです。
当園で月に約一度「SI遊び」を行っていますが、じっくり考える子と、そうでない子の差がはっきり見えてきます。
集中力をつけさせる「SI遊び」が、いい訓練の場になっている気がします。
集中力をつけさせる「SI遊び」が、いい訓練の場になっている気がします。
まずは、今、普段何気なく見ているTVのスイッチを一日でも切ってみることをお勧めします。