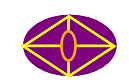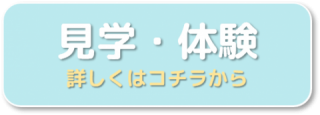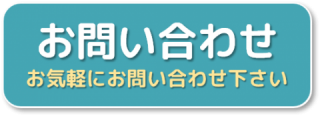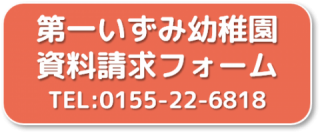園長通信
園長先生からのメッセージ
20.忘れてはならないこと
2011-12-20
ふりかえると、2011年は歴史に残る忘れることのできない大きなことのあった年でした。特に原発問題は全ての日本人に大きな驚きと、改めて放射能に対する警鐘を鳴らしたかつてない事件でした。
言わずもがな、3.11以前と以降ではいろいろなことが変わってくるでしょう。
津波の恐ろしさ。エネルギー問題。電気の大切さ。当たり前のことが当たり前ではないということ。豊かな暮らしは永遠ではないということ。食べること。住むこと。そして生きることの大切さ。人間のたくましさ。そして人と人の「絆」。
多くのことが私たちに投げかけ、問いかけています。答えは、一人一人が考えること・・
2011年、私は震災後すぐに現地に入りたかったのですが、それも叶えられず、悶々としていましたが、やっと機会があって9月の末と10月の末に2回、陸前高田にボランティアで現地入りしてきました。仕事内容は瓦礫の撤去、分別でしたが、現地で最初に飛び込んできたうず高く積まれた瓦礫の量に圧倒されてしまいました。そこらじゅうに散らばっていた瓦礫は集約されて何箇所かに集められていました。何もないフラットな町。まさにグランドゼロとでもいうのでしょうか。ここに人が住む事がホントにできるのだろうか、と考えました。
今回、札幌と東京から入ったわけですが、様々な人が、まさに年齢も様々で老若男女が全国から集まっていました。みんな、意気揚々と積極的に参加されていて、言葉を交わさなくても同じ意識をもった同志の連帯感を感じました。
いわき市にある、知り合いの幼稚園にもいろいろ援助しました。放射能の影響はほんとに目に見えないもので無色無臭なのでやっかいです。福島の方々のご苦労の大変さは現地で感じないとわからないでしょう。特に未来に向かって生きている子ども達には深刻な問題です。外に出れない。大空の下で遊べない。という状況は想像を超えています。その気持ちを考えるとやるせない気になります。当たり前のことが当たり前ではないのです。現地に何かをと、やはり子どもたちの手作りのものを送りました。確実に収束に向かっているのですが、簡単に収束などとは言えない状況があります。
子ども達にも、同じお友だちがたいへんだけどがんばっているんだよ。応援してあげてね。と感じ取ってもれえればと思いました。
外にいつでも出れる、思いっきり息を吸える。これから私達の生活も、忘れていたことを思い出して、便利さだけにおぼれないように。当たり前のことに感謝して。
さらには被災地のことをずっと忘れないように生きていかないといけないと感じました。
19.ポジティブ ワードが子どもを伸ばす 〜 魔法の言葉力
2011-03-11
いよいよ卒園も間近になってきました。
園に対するいろいろご協力ありがとうございました。
最後になりますが小学校に上がるうえでお伝えしたいと思います。
ご存知のように子どもに対する親のことばの影響力は大きなものがあります。
あの盲目の天才ピアニスト辻井伸行君のお母さん(辻井いつ子さん)が出している本にこんな一説があります。
私は子育ての間は、できるだけネガティブ・ワードは使わないようにしてきました。「できない」「だめ」「分からない」などなど。
生活の中で人は無意識に、ネガティブな言葉を使ってしまいます。
もちろんできないことはできないし、無理なことは無理なのですが、チャレンジする前から「無理」「できない」などと言ってしまったら、最初から精神が縮んでしまうように思うのです。
そうではなく、何か課題が出てきたら、「やってみよう」「挑戦してみよう」といった言葉に出して行動するように心がけてきました。
というように、言葉の力の大切さを述べています。子どもには挑戦する言葉を投げかけてやることが必要です。それはその子の未来に通じていることだからです。現実の中でどうしてもネガティブに言いがちになる言葉ですが、少し心がけることで子どもはとても勇気付けられます。
いつでも「やればできる」「行動を起こせば必ず結果はついていくる」といった気持ちで子どもにアクションを起こしてみてください。このポジティブ・ワード、そしてポジティブ・シンキングが大きな変化、そして大きな夢につながっていくかもしれません。
それと、関連して、親の「望み」と子どもの「好き」の関係についても大切なポイントがあります。女の子だと、小さいころは「女の子らしく」とかピアノを習わせたり、また男のなら、「男の子らしく」といった勝手にイメージをふくらませることがあります。
子どもの「好き」ではなく、親の「望み」が勝ってしまう。ということです。
世間や親の常識にわが子を押し込んでしまうことがありませんか?
今の時代、ずいぶん女の子も変わってきて社会にでてくる世の中です。女の子、男の子という垣根もなくなってきています。
親の価値観で子どもの「好き」を限定しないことです。小さいうちは何が向いているかがわからないかも知れません。でも見方を変えてよく見てみると子どもの「好き」が分かってきます。個性は「宝」にもなります。子どもの長所を最大限に発揮できる「環境」をつくるのも親として大事な責任です。そういった親の一生懸命な姿勢が子どもに伝わります。「親が力強い見方になってくれる」といった精神的なよりどころ、安定した気もちが子ども、子育てに重要になってきます。
園ではいろいろなきっかけを与えました。これからが個性が開花していくときかもしれません。ぜひ純粋な動機で子どもの「好き」に関わってあげてください。あきらめることなく。
辻井いつ子さんの本もぜひ読んでみてください。とても読みやすい本です。おもしろい逸話が満載です。
余談ですが辻井伸行君が世界的に有名な国際コンクールで日本人初の優勝したのが2009年で21歳のときです。それ以来世界中からオファーがきているそうです。そしてつい先日あのNYの殿堂、カーネギーホールから出演依頼があったそうです。すごいことですね。日本人として応援していきたいですね。
ありがとうございました。 園長 遠藤崇浩
ありがとうございました。 園長 遠藤崇浩
「園長あいさつ」
2010-04-07
「三つ子の魂百まで」ということわざがありますが、それは幼児期の子育てのあり方が人の一生の心の持ち方(心情や意欲)や生活態度などに強い影響を与えるからです。だから、子供の育つ環境をよく整えて、子供の発達に即したものを準備しなければならないという意味です。
幼稚園の教育は即ち人間の基礎を作るところです。その基礎を作る上で”遊びを通した集団生活”は欠かせないものになってきています。家族の中で関わってきた幼児も2〜3歳頃から、友達を求めるようになります。又好奇心が生まれ、未知の世界を憧れるようになります。3〜4歳になると子供は自然にお母さんと遊ぶだけでなく、同年齢の子供一緒にいることを喜ぶようになります。いつまでも狭い親の手元に閉じこめないで、新しい世界に幼児を送り出すことが必要です。
幼稚園はそうした子どもたちがたくさん集まって一緒に遊んだり、生活をする場です。
多くの友達と出会い、また先生と出会い、集団生活の中で新しい経験を通じ、友達と関わり、言葉や生活習慣、豊かな心や物事に集中して取り組む姿勢を自然に身につけて行きます。
私たちは豊かな人間性や社会性をそなえ、そして国際社会に生きる人間の基礎を育てるため、生きる力(好奇心・探求心・問題を自分で解決する力・豊かな感性)をもったたくましい子・自信を持った子を育てて行きたいと考えています。そのためには、御家庭の協力を得ながら優れた教師、情操にあふれた保護者が両輪となって、力を合わせることが必要です。
そして、その上に子供を乗せて、ひとりひとりが豊かな人間になっていくよう毎日の教育にあたっていく所存です。
帯西幼稚園園長 遠藤崇浩
幼稚園の教育は即ち人間の基礎を作るところです。その基礎を作る上で”遊びを通した集団生活”は欠かせないものになってきています。家族の中で関わってきた幼児も2〜3歳頃から、友達を求めるようになります。又好奇心が生まれ、未知の世界を憧れるようになります。3〜4歳になると子供は自然にお母さんと遊ぶだけでなく、同年齢の子供一緒にいることを喜ぶようになります。いつまでも狭い親の手元に閉じこめないで、新しい世界に幼児を送り出すことが必要です。
幼稚園はそうした子どもたちがたくさん集まって一緒に遊んだり、生活をする場です。
多くの友達と出会い、また先生と出会い、集団生活の中で新しい経験を通じ、友達と関わり、言葉や生活習慣、豊かな心や物事に集中して取り組む姿勢を自然に身につけて行きます。
私たちは豊かな人間性や社会性をそなえ、そして国際社会に生きる人間の基礎を育てるため、生きる力(好奇心・探求心・問題を自分で解決する力・豊かな感性)をもったたくましい子・自信を持った子を育てて行きたいと考えています。そのためには、御家庭の協力を得ながら優れた教師、情操にあふれた保護者が両輪となって、力を合わせることが必要です。
そして、その上に子供を乗せて、ひとりひとりが豊かな人間になっていくよう毎日の教育にあたっていく所存です。
帯西幼稚園園長 遠藤崇浩
1.「しつけ」
2010-04-07
子供を怒ることはたやすい。しかし「しつけ」となるとまた別である。
子供をどう怒るか、これが難しい。ここが子育ての根幹でもある。
つまり子供は親のある意味、完全支配化にある存在である。それだけに親も子に対して気ままになりやすい。つまり禁止語が多くなり、感情のままに振舞いがちになる。子供に対して親が気ままになればなるほど、子供もまた自分の気持ちをコントロールする術を身に付けようとせず、確実に気ままな人間になる。
これがこのままの状態で大人になると大変である。
気ままな子供の親は必ずと言っていいほど気ままである。幼稚園と家庭における接している時間の違いからも一番の影響は明らかである。
怒りに押し流されていると「しつけ」にはほど遠く、問題はいつまでも解決はしない。ただし、たまにカミナリを落とすことはいいが、毎日ガミガミでは確実に子供は被害者になる。
感情の爆発を避けるにはやはりワンクッション置くことが大切である。一回深呼吸して冷静に自分を見つめることをお勧めする。
しかし思うに、人間から完全に気ままを取り去ることはできない。が、それを抑え、コントロールすることはできるはずだ。つまり耐え忍ぶこと、今、我慢ができない子供が増えている。その力をつけるのが「しつけ」であり、教育なのである。しつけは「し続ける」とも書く。三日坊主で終わることなく、日々重ねていかないと身につかない。
父親、母親と、それぞれの役割を分担して日々変えていかないと手遅れになってしまう。子供のときに身に付けた「しつけ」は一生消えるものではないという。年齢に「つ」がつくまでが勝負であるということです。(九つまで) あとわずかで迎える、21世紀を機会にスタートしてみてはいかがでしょう。
子供をどう怒るか、これが難しい。ここが子育ての根幹でもある。
つまり子供は親のある意味、完全支配化にある存在である。それだけに親も子に対して気ままになりやすい。つまり禁止語が多くなり、感情のままに振舞いがちになる。子供に対して親が気ままになればなるほど、子供もまた自分の気持ちをコントロールする術を身に付けようとせず、確実に気ままな人間になる。
これがこのままの状態で大人になると大変である。
気ままな子供の親は必ずと言っていいほど気ままである。幼稚園と家庭における接している時間の違いからも一番の影響は明らかである。
怒りに押し流されていると「しつけ」にはほど遠く、問題はいつまでも解決はしない。ただし、たまにカミナリを落とすことはいいが、毎日ガミガミでは確実に子供は被害者になる。
感情の爆発を避けるにはやはりワンクッション置くことが大切である。一回深呼吸して冷静に自分を見つめることをお勧めする。
しかし思うに、人間から完全に気ままを取り去ることはできない。が、それを抑え、コントロールすることはできるはずだ。つまり耐え忍ぶこと、今、我慢ができない子供が増えている。その力をつけるのが「しつけ」であり、教育なのである。しつけは「し続ける」とも書く。三日坊主で終わることなく、日々重ねていかないと身につかない。
父親、母親と、それぞれの役割を分担して日々変えていかないと手遅れになってしまう。子供のときに身に付けた「しつけ」は一生消えるものではないという。年齢に「つ」がつくまでが勝負であるということです。(九つまで) あとわずかで迎える、21世紀を機会にスタートしてみてはいかがでしょう。
2.「自信のある積極的な子にするコツ」
2010-04-07
たとえば子供の安全を願い、失敗しないようにと常に配慮するといったことは親として
ごく当たり前のことですが、度を超せば、過保護、過干渉となって、結果依存性の高い子を作り上げてしまいます。
親と一緒の時は自分で考えなくてもみんなやってもらえるのですが、一人で判断して決定し、実行に移さなければならない場面では、すっかり途方に暮れてしまうといった結果になりかねません。
過保護や過干渉をやっている親が、依頼心の強い子にしようなどは毛頭思っておらず、自信があって積極的な子に育って欲しいという願いをむしろ強く持っている場合があります。非常に矛盾しています。だからこの矛盾に気づき抜け出せばいいわけです。
育児書に振り回されない、よその子と自分のことが競争しているかのように、些細なことで一喜一憂する「比較育児」の落とし穴にはまらない。
子供が自ら「生きよう」という育つ力を内面に持っていることを固く信じて「私の子だ大丈夫、いい子に育ってくれる」と常に思いこむことが大切です。
そんな親の自信に満ちた情緒の安定した態度こそが、子供に伝わるのです。
例えば「おかあさん、僕何回練習しても”さか上がり”できないんだよ。A君もBちゃんもできるのに…」とこぼすK君を見てお母さんは私に似て運動神経が今ひとつだなと思いました。お父さんはその時「お父さんは子供のときうまくやれたけど…今度やってみるか。」と次の休みに公園で練習をしました。
お父さんから「もっとこうしなさい」と握り方や力を入れるコツを教えてもらったり、K君はその日さか上がりは出来ませんでしたが、お父さんに相手してもらってとっても満足でした。
K君の両親はK君がやりたがることは何でもやらせる主義でした。「危ないからやめなさい」や「そんなことしたってお前はまだムリだよ」といったある意味大人の予想から言うことはしないで、「やろうとしただけでも偉いじゃないか」とむしろ励ましたりしました。
ここが大事なことです。
得意、不得意は誰にだってあります。自信は最初からあるのではないということです。
失敗したときに何度でも上手に付き合ってくれる人がいれば、子供は何度でもチャレンジするものです。むしろ失敗する自由を保障してあげて、うまく行ったときはたくさんほめてあげること。これが自信のあるたくましい子にするコツです。
ごく当たり前のことですが、度を超せば、過保護、過干渉となって、結果依存性の高い子を作り上げてしまいます。
親と一緒の時は自分で考えなくてもみんなやってもらえるのですが、一人で判断して決定し、実行に移さなければならない場面では、すっかり途方に暮れてしまうといった結果になりかねません。
過保護や過干渉をやっている親が、依頼心の強い子にしようなどは毛頭思っておらず、自信があって積極的な子に育って欲しいという願いをむしろ強く持っている場合があります。非常に矛盾しています。だからこの矛盾に気づき抜け出せばいいわけです。
育児書に振り回されない、よその子と自分のことが競争しているかのように、些細なことで一喜一憂する「比較育児」の落とし穴にはまらない。
子供が自ら「生きよう」という育つ力を内面に持っていることを固く信じて「私の子だ大丈夫、いい子に育ってくれる」と常に思いこむことが大切です。
そんな親の自信に満ちた情緒の安定した態度こそが、子供に伝わるのです。
例えば「おかあさん、僕何回練習しても”さか上がり”できないんだよ。A君もBちゃんもできるのに…」とこぼすK君を見てお母さんは私に似て運動神経が今ひとつだなと思いました。お父さんはその時「お父さんは子供のときうまくやれたけど…今度やってみるか。」と次の休みに公園で練習をしました。
お父さんから「もっとこうしなさい」と握り方や力を入れるコツを教えてもらったり、K君はその日さか上がりは出来ませんでしたが、お父さんに相手してもらってとっても満足でした。
K君の両親はK君がやりたがることは何でもやらせる主義でした。「危ないからやめなさい」や「そんなことしたってお前はまだムリだよ」といったある意味大人の予想から言うことはしないで、「やろうとしただけでも偉いじゃないか」とむしろ励ましたりしました。
ここが大事なことです。
得意、不得意は誰にだってあります。自信は最初からあるのではないということです。
失敗したときに何度でも上手に付き合ってくれる人がいれば、子供は何度でもチャレンジするものです。むしろ失敗する自由を保障してあげて、うまく行ったときはたくさんほめてあげること。これが自信のあるたくましい子にするコツです。