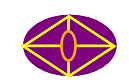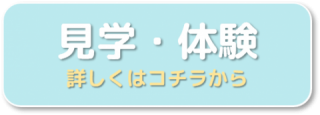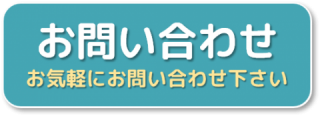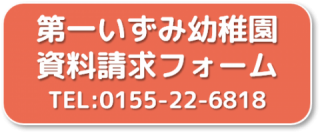園長通信
園長先生からのメッセージ
8.家族
2010-04-07
家族について考えてみたいと思います。
さきごろ興味深い論説があったので御紹介したいと思います。
核家族が3世代目に突入した時代を迎えたそうです。そんな中で日本の家族の形態もかわりつつあるようです。
自分の家族さえよければいいという内向きの風潮が広まっているということです。
家庭の中心にあるものを聞くと80年代「テレビ」だったのが今は「何もない」という答えが多い、空洞感が広がっています。
日本人は「外は大変だから家の中だけは幸せにしたい」と思いたがる発想が増えているそうです。
戦時中ならまだしも、こんな平和な時代でも妙な解釈をしてしまう。「この子には苦労させたくない…」などといった苦労知らずの親が子供のやらねばならないことを無意識に奪ってしまっている現実。
自立させなければならないのにかわいさ余って問題、障害を与えないで守りすぎる、
だから「できない」、「やれない」を連発する。その結果大人になっても殻に閉じこもってしまうひ弱な人間が増えてしまうのです。そしてあるときのそのストレスを爆発させる…
家族にしても、結局、夫婦や親子がそれぞれの生き方をじっくり語ったり、人間対人間がぶつかり合ったりすることもなかったのです。思春期の子供に必要な議論や会話も欠落してしまったのです。言いたいことが言えない環境はストレスがたまります。結果、子供も「家に帰りたくない…」とこうなります。
家族という最小のユニットのあり方にある根本の問題にふたをしてきたとも言えます。
あらためて自分にとって「家族とは何か」を考えていく必要があるようです。
さきごろ興味深い論説があったので御紹介したいと思います。
核家族が3世代目に突入した時代を迎えたそうです。そんな中で日本の家族の形態もかわりつつあるようです。
自分の家族さえよければいいという内向きの風潮が広まっているということです。
家庭の中心にあるものを聞くと80年代「テレビ」だったのが今は「何もない」という答えが多い、空洞感が広がっています。
日本人は「外は大変だから家の中だけは幸せにしたい」と思いたがる発想が増えているそうです。
戦時中ならまだしも、こんな平和な時代でも妙な解釈をしてしまう。「この子には苦労させたくない…」などといった苦労知らずの親が子供のやらねばならないことを無意識に奪ってしまっている現実。
自立させなければならないのにかわいさ余って問題、障害を与えないで守りすぎる、
だから「できない」、「やれない」を連発する。その結果大人になっても殻に閉じこもってしまうひ弱な人間が増えてしまうのです。そしてあるときのそのストレスを爆発させる…
家族にしても、結局、夫婦や親子がそれぞれの生き方をじっくり語ったり、人間対人間がぶつかり合ったりすることもなかったのです。思春期の子供に必要な議論や会話も欠落してしまったのです。言いたいことが言えない環境はストレスがたまります。結果、子供も「家に帰りたくない…」とこうなります。
家族という最小のユニットのあり方にある根本の問題にふたをしてきたとも言えます。
あらためて自分にとって「家族とは何か」を考えていく必要があるようです。
9.お別れ会が終わって
2010-04-07
お別れ会が終わりました。毎年この時期になってくると卒園を意識しだします。
教師ばかりではなく、子供自身も年長はもちろんの事、年中、年少児も自分がこれから大きくなるんだ、大きい組のお兄さん、お姉さんはあらためてすごいということを意識しだします。
今年の年長さんの歌は特に立派でした。声がそろっていて、自信にみなぎった力強い歌でした。おもわず感動しました。
自分達が小学校に上がること、自分たちは幼稚園ともあとわずかでお別れだということ、いいところを見せようということではなく、自然な今まで培った自信みたいなものがみなぎってました。
まさに年長の最後の歌にふさわしいものでした。こんなに年長がまとまって歌に集中しているのも久しぶりに見た気がします。
誰一人ふざけている子はいません。全員が伸び伸びと歌を楽しんでいるのです。こんなに立派になっている子供に親は気づいているでしょうか。
「生きる力を持ったたくましい子を育てる」のは簡単なことではありません。しかしここに見る年長の姿はまさしく、たくましく生きていこうという姿勢がみなぎっていました。地道にやってきた保育が完成期の今、花開くようです。それは教師みんなが感じたことです。
でも卒業なんですね…もっともっといろんなことができる、させたいという思いが強くなるのは私だけではないはすです。
子供の自発性の芽をぜひつぶさないようにしていただきたいと願うばかりです。
教師ばかりではなく、子供自身も年長はもちろんの事、年中、年少児も自分がこれから大きくなるんだ、大きい組のお兄さん、お姉さんはあらためてすごいということを意識しだします。
今年の年長さんの歌は特に立派でした。声がそろっていて、自信にみなぎった力強い歌でした。おもわず感動しました。
自分達が小学校に上がること、自分たちは幼稚園ともあとわずかでお別れだということ、いいところを見せようということではなく、自然な今まで培った自信みたいなものがみなぎってました。
まさに年長の最後の歌にふさわしいものでした。こんなに年長がまとまって歌に集中しているのも久しぶりに見た気がします。
誰一人ふざけている子はいません。全員が伸び伸びと歌を楽しんでいるのです。こんなに立派になっている子供に親は気づいているでしょうか。
「生きる力を持ったたくましい子を育てる」のは簡単なことではありません。しかしここに見る年長の姿はまさしく、たくましく生きていこうという姿勢がみなぎっていました。地道にやってきた保育が完成期の今、花開くようです。それは教師みんなが感じたことです。
でも卒業なんですね…もっともっといろんなことができる、させたいという思いが強くなるのは私だけではないはすです。
子供の自発性の芽をぜひつぶさないようにしていただきたいと願うばかりです。
10.テレビについて
2010-04-07
最近テレビに釘付けになっているご家庭が多いかと思います。
夜遅くまでお子さんが起きていて、親の寝る時間と一緒になってはいないでしょうか。
今回は普段何気なく見ているテレビの効用についてお話したいと思います。
最近お父さんの子育て参加が増えています。とてもいいことですが、「忙しくて子供と話す機会がない」とぼやくお父さんもまだまだいるのも現実です。
しかし、以外にテレビがじゃましているのに気がついていないことがあります。
週に一度テレビを見ない日を設けている家があります。その日はテレビのスイッチを一切入れないそうです。
それからは家族の会話が目立って増えて子供や、家族のことがよくわかったということです。
普段、当たり前のようにつけているテレビの習慣を変えるのは難しいことですが、時間を区切ってもいいかと思います。
特に食事中のながら鑑賞はだらだらと食べるくせにもなっていきますし決してよいことはありません。
ここからはじめてもいいかと思います。
せめて食事のときだけはテレビをつけないのはいかがでしょうか。
最初は大変ですが、習慣化すればしめたものです。ビデオはどの家庭にもありますし。
ラジオを情報源にしている家庭もあります。それもいいかと思います。
このようにどんなにお父さんが忙しくても、その気になって工夫をこらせば、家族で会話する機会はいくらでも作れるはずです。
忙しさを口実に怠慢を決め込んではいないでしょうか。
またテレビと子供の言語発達には深い関係があるのもご存知でしょうか。
ある機関が幼稚園児とテレビの関係について調査したところ一日30分テレビを見る子と、一日3時間見る子を比較したら、前者の語彙集が約6000だったのに対し、後者の語彙集は半分の約3000だったということです。
テレビは視覚と聴覚に訴えて情報を伝達するメディアです。
これだけみると言語能力が豊かになりそうに思いますが、そうならないのはなぜか。
テレビの番組にはいろいろありますが、圧倒的に多いのは各種の娯楽番組です。
そして画像と音とどちらが中心かといえば画像です。動く絵というのが特徴です。
音は画像を補う役割がテレビなわけです。
テレビのほうがこま切れの語彙が多く含まれ、決まった表現しかできなくなっているのです。
バラエティー番組などはその最たるものです。
最近の若者たちの表現力の低下はまちがいなくここから来ています。
表現ができない分、欲求不満がたまり、暴力的になるのも一因かと思います。
若者同士の会話ならいいが、しかしそれでは社会に通用しないのです。
また、乏しい言語はいろいろなところで、知らないうちに摩擦を作ってしまいがちです。
では言語能力を豊かにするにはどうするか。
テレビよりも本を読むことを提唱します。
親が読んでやる本は受身のテレビよりもはるかに想像力を刺激して、親子の生の会話が楽しめます。
子供も安定してきます。たまにお父さんが読んであげるとどんなにかうれしいことでしょう。
テレビならではの効果も確かにあります。否定はしません。
しかしテレビの見すぎだけはいけません。
テレビの見る時間のバランスをおかあさんやお父さんがつくってあげることが絶対必要です。
普段の生活を変えていくのは親がまず変えていかないといけません。
お子さんのためにも、まず、日常を見直してください。
夜遅くまでお子さんが起きていて、親の寝る時間と一緒になってはいないでしょうか。
今回は普段何気なく見ているテレビの効用についてお話したいと思います。
最近お父さんの子育て参加が増えています。とてもいいことですが、「忙しくて子供と話す機会がない」とぼやくお父さんもまだまだいるのも現実です。
しかし、以外にテレビがじゃましているのに気がついていないことがあります。
週に一度テレビを見ない日を設けている家があります。その日はテレビのスイッチを一切入れないそうです。
それからは家族の会話が目立って増えて子供や、家族のことがよくわかったということです。
普段、当たり前のようにつけているテレビの習慣を変えるのは難しいことですが、時間を区切ってもいいかと思います。
特に食事中のながら鑑賞はだらだらと食べるくせにもなっていきますし決してよいことはありません。
ここからはじめてもいいかと思います。
せめて食事のときだけはテレビをつけないのはいかがでしょうか。
最初は大変ですが、習慣化すればしめたものです。ビデオはどの家庭にもありますし。
ラジオを情報源にしている家庭もあります。それもいいかと思います。
このようにどんなにお父さんが忙しくても、その気になって工夫をこらせば、家族で会話する機会はいくらでも作れるはずです。
忙しさを口実に怠慢を決め込んではいないでしょうか。
またテレビと子供の言語発達には深い関係があるのもご存知でしょうか。
ある機関が幼稚園児とテレビの関係について調査したところ一日30分テレビを見る子と、一日3時間見る子を比較したら、前者の語彙集が約6000だったのに対し、後者の語彙集は半分の約3000だったということです。
テレビは視覚と聴覚に訴えて情報を伝達するメディアです。
これだけみると言語能力が豊かになりそうに思いますが、そうならないのはなぜか。
テレビの番組にはいろいろありますが、圧倒的に多いのは各種の娯楽番組です。
そして画像と音とどちらが中心かといえば画像です。動く絵というのが特徴です。
音は画像を補う役割がテレビなわけです。
テレビのほうがこま切れの語彙が多く含まれ、決まった表現しかできなくなっているのです。
バラエティー番組などはその最たるものです。
最近の若者たちの表現力の低下はまちがいなくここから来ています。
表現ができない分、欲求不満がたまり、暴力的になるのも一因かと思います。
若者同士の会話ならいいが、しかしそれでは社会に通用しないのです。
また、乏しい言語はいろいろなところで、知らないうちに摩擦を作ってしまいがちです。
では言語能力を豊かにするにはどうするか。
テレビよりも本を読むことを提唱します。
親が読んでやる本は受身のテレビよりもはるかに想像力を刺激して、親子の生の会話が楽しめます。
子供も安定してきます。たまにお父さんが読んであげるとどんなにかうれしいことでしょう。
テレビならではの効果も確かにあります。否定はしません。
しかしテレビの見すぎだけはいけません。
テレビの見る時間のバランスをおかあさんやお父さんがつくってあげることが絶対必要です。
普段の生活を変えていくのは親がまず変えていかないといけません。
お子さんのためにも、まず、日常を見直してください。
11.テレビが子供の脳を壊す
2010-04-07
実は前回TVについてお話しましたが、7月15日付の週刊アエラに、上記のタイトルのようなショッキングな記事がタイムリーにのっていました。
見られた方もいると思いますが、その中でカラーテレビとともに育ったテレビ第一世代が親になり、つけっぱなしにしても何も違和感がない状況。
そして今では、その視聴の対象はビデオやテレビゲームなどの普及が、長時間視聴に拍車をかけているということです。
見られた方もいると思いますが、その中でカラーテレビとともに育ったテレビ第一世代が親になり、つけっぱなしにしても何も違和感がない状況。
そして今では、その視聴の対象はビデオやテレビゲームなどの普及が、長時間視聴に拍車をかけているということです。
2歳6ヶ月のA君は11ヶ月で歩き、語彙数も豊富であった。しかしその後、教師の母親が職場に復帰、祖母に預けられた半年で、A君から言葉が消えた。返事もしなければ、家族とも目を合わせない。そして一人遊びが増え、たびたび暴れるようになった。
A君を調べてみると、テレビを見る時間が急増。一日に見る時間はアンパンマンのビデオにはじまり、一日8時間にもなっていたということです。
言葉の遅れは先天的な要因だと考えられていましたが、いまテレビ、ビデオ付けの生活で「新しいタイプの言葉遅れ」が増えているそうです。
A君を調べてみると、テレビを見る時間が急増。一日に見る時間はアンパンマンのビデオにはじまり、一日8時間にもなっていたということです。
言葉の遅れは先天的な要因だと考えられていましたが、いまテレビ、ビデオ付けの生活で「新しいタイプの言葉遅れ」が増えているそうです。
こうした子はおとなしく、手がかからない一見いい子であるが、言葉が遅れると、自分の意思を伝えたり、聞いて判断するという「考える力」が育たなくなります。
4歳、5歳までこのままだったら、言葉や考える力を完全に取り戻すことは非常に難しくなります。
4歳、5歳までこのままだったら、言葉や考える力を完全に取り戻すことは非常に難しくなります。
ある統計で特に長時間だった子供の行動を観察すると、共通した特徴が「友達関係がもてない」「表情が乏しい」「視線が合わない」「遊びが限られる」「話し言葉に抑揚がない」・・など、特徴の多くは自閉症の子供に似ているそうです。
北大の沢口教授によりますと「ADHD(注意欠陥多動症)の急増などはテレビ付けの環境が影響を及ぼしていると考えざるを得ない。」と言ってます。
沢口教授が危惧しているのは、テレビを子守がわりにすることによって、子供が母親から引き離されることであって、脳の発達に必要な双方向の刺激、つまり母親とのコミュニケーションがとれなくなることだそうです。ほんとに怖いことですね。
沢口教授が危惧しているのは、テレビを子守がわりにすることによって、子供が母親から引き離されることであって、脳の発達に必要な双方向の刺激、つまり母親とのコミュニケーションがとれなくなることだそうです。ほんとに怖いことですね。
今問われているのは「見方」「見せ方」だそうです。
ある地域で月に一度「ノーテレビデー」を1年間続けたら、叩く、蹴るという攻撃的な行動が減って、「やだ」「死ね」という単語でしか話せなかった子が、文章の形で話せるようになったという報告が出ています。
ある地域で月に一度「ノーテレビデー」を1年間続けたら、叩く、蹴るという攻撃的な行動が減って、「やだ」「死ね」という単語でしか話せなかった子が、文章の形で話せるようになったという報告が出ています。
最初はやるのは大変ですが、次第に慣れさせていくと、あっけないほど子供は順応してしまい、一度「退屈する自由」を経験すると、子供たちは初めて自分で自発的に考え、遊び始めるようです。
当園で月に約一度「SI遊び」を行っていますが、じっくり考える子と、そうでない子の差がはっきり見えてきます。
集中力をつけさせる「SI遊び」が、いい訓練の場になっている気がします。
集中力をつけさせる「SI遊び」が、いい訓練の場になっている気がします。
まずは、今、普段何気なく見ているTVのスイッチを一日でも切ってみることをお勧めします。
12.育つ力
2010-04-07
子どもに目標を持たせることは大切なことです。
漠然とやらせるのではなく、少しづつ目標をあせらずやらせる、そしてできたらほめてやる。又目標を与える。
その繰り返しが子どもの成長をぐんぐん伸ばします。
もともと子ども自身の中に伸びようとする力が備わっているんです。
そのときに大人がどう関わってやれるかです。
発表会はそういう意味で一つの目標です。
子どもたちはそれぞれの目標に向けて全力でがんばっています。
ずいぶんできるようになってきました。年長の運動あそび、年中、年少のお遊戯。
「僕、もう〜・・出来るようになったんだよ。私こんなに出来るようになったんだよ。」口々に報告してくれます。
発表会が待ち遠しいようです。ここまでくるには、たくさんの子どもなりの葛藤があったようです。
でもお友達同士のかかわりの中で、教師の助言の中で、くじけないでがんばる力が育まれていくんですね。
人間は、環境の中で変化する動物です。
特に就学前の子どものこの時期はとても影響力があります。
たくさんの葛藤の中で、生きていく力が養われます。
子どもの成長点を常に意識しながら、ここを伸ばそう、ここは黙っていようなど大人の関わりは大切です。
たくさんの先生に、大人に囲まれて人間は成長していくんですね。
幼稚園の2学期はとても子どもが成長する時期です。ご家庭での協力も大切です。たくさん励ましてあげてくださいね。
漠然とやらせるのではなく、少しづつ目標をあせらずやらせる、そしてできたらほめてやる。又目標を与える。
その繰り返しが子どもの成長をぐんぐん伸ばします。
もともと子ども自身の中に伸びようとする力が備わっているんです。
そのときに大人がどう関わってやれるかです。
発表会はそういう意味で一つの目標です。
子どもたちはそれぞれの目標に向けて全力でがんばっています。
ずいぶんできるようになってきました。年長の運動あそび、年中、年少のお遊戯。
「僕、もう〜・・出来るようになったんだよ。私こんなに出来るようになったんだよ。」口々に報告してくれます。
発表会が待ち遠しいようです。ここまでくるには、たくさんの子どもなりの葛藤があったようです。
でもお友達同士のかかわりの中で、教師の助言の中で、くじけないでがんばる力が育まれていくんですね。
人間は、環境の中で変化する動物です。
特に就学前の子どものこの時期はとても影響力があります。
たくさんの葛藤の中で、生きていく力が養われます。
子どもの成長点を常に意識しながら、ここを伸ばそう、ここは黙っていようなど大人の関わりは大切です。
たくさんの先生に、大人に囲まれて人間は成長していくんですね。
幼稚園の2学期はとても子どもが成長する時期です。ご家庭での協力も大切です。たくさん励ましてあげてくださいね。