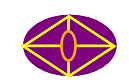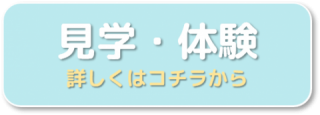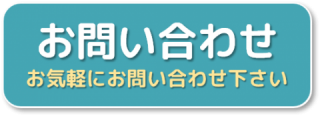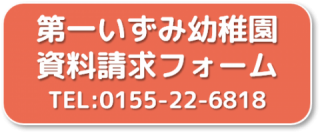園長通信
園長先生からのメッセージ
13.本物.
2010-04-07
2学期も終わりました。大きな成長が、このやはり2学期にあったのではないかと思います。
子供の成長は集団生活で飛躍的に伸びるといってもいいでしょう。
でも、家庭での安定や、基礎があってのことです。
最近、思うことは経済の危機(デフレ等)、政治の危機(不祥事の連続)が変わらずあります。
しかし、これも今、大きな変わり目と考えると、
2〜3年で自己回復力をもって立ち直る時期が必ずくるのではと考えているのです。
しかし、教育の危機の回復は、どう見ても10年から20年かかると考えます。
ものがあまっている社会の中で、豊かになった社会の反動が確実に精神を蝕んでいます。
お小遣いとおもちゃと携帯を自由に与えてきたそのツケが始まっているのです。
親子の会話もなく、父親の威厳もなく、しつけをしてこなかった親や教師。
礼儀を知らない親、または省略してしまった親や教師、ただそれをみて当たり前のように育った子供たち。
彼らが本当に悪いといえるのでしょうか。
当たり前のことができなくなっていると感じています。
特に豊かな時代の反動の象徴としてあるのが我慢、忍耐力のない子供。大人もそうです。
「歯をくいしばって」、「鍛錬」などという言葉は死語にもなっているといわれています。
豊か過ぎる時代の代償は大きく、次の世代に大変な影響を与えていると自覚すべきではないでしょうか。
にせものが多くなっているのも時代の象徴です。と同時に、本物志向もでてきました。
園でも極力、本物を与えるようにしていますが、園だけでは不十分で、子供の環境は確実に悪くなっています。
例えば、クリスマスのシーズンのとき出てくる、無数の擬似サンタ。
自分の時代の話で恐縮ですが、昔はサンタは一種、神がかっていました。
情報もそんなに多くなかったから、あの赤い服だけでドキドキした思い出があります。
今ではあちこちにサンタが出没しています。どれが本当のサンタさん?
「みんな人が入ってやってるんだね。」「本当は誰々だよね」。
そんな、なまいきな言葉が子供たちから聞こえてきそうです。
ご家庭では、サンタをどんなふうに説明していますか?いやそれとも説明などしていませんか?
こんな時代、情報過多の時代だからこそ本物に大人が触れさせることが大事です。
大人には説明責任があるのです。本物を伝えましょう。
そしていい悪いの善悪の判断を親が責任もって示してやることが大事です。ダメなことはダメというけじめ。
冬休み、家庭にいる時間が長くなります。子供といろんなことを話す時間を創りましょう。
TVに時間を持っていかれないように、向かい合いましょう。いろいろな発見がきっとあると思いますよ。
子供の成長は集団生活で飛躍的に伸びるといってもいいでしょう。
でも、家庭での安定や、基礎があってのことです。
最近、思うことは経済の危機(デフレ等)、政治の危機(不祥事の連続)が変わらずあります。
しかし、これも今、大きな変わり目と考えると、
2〜3年で自己回復力をもって立ち直る時期が必ずくるのではと考えているのです。
しかし、教育の危機の回復は、どう見ても10年から20年かかると考えます。
ものがあまっている社会の中で、豊かになった社会の反動が確実に精神を蝕んでいます。
お小遣いとおもちゃと携帯を自由に与えてきたそのツケが始まっているのです。
親子の会話もなく、父親の威厳もなく、しつけをしてこなかった親や教師。
礼儀を知らない親、または省略してしまった親や教師、ただそれをみて当たり前のように育った子供たち。
彼らが本当に悪いといえるのでしょうか。
当たり前のことができなくなっていると感じています。
特に豊かな時代の反動の象徴としてあるのが我慢、忍耐力のない子供。大人もそうです。
「歯をくいしばって」、「鍛錬」などという言葉は死語にもなっているといわれています。
豊か過ぎる時代の代償は大きく、次の世代に大変な影響を与えていると自覚すべきではないでしょうか。
にせものが多くなっているのも時代の象徴です。と同時に、本物志向もでてきました。
園でも極力、本物を与えるようにしていますが、園だけでは不十分で、子供の環境は確実に悪くなっています。
例えば、クリスマスのシーズンのとき出てくる、無数の擬似サンタ。
自分の時代の話で恐縮ですが、昔はサンタは一種、神がかっていました。
情報もそんなに多くなかったから、あの赤い服だけでドキドキした思い出があります。
今ではあちこちにサンタが出没しています。どれが本当のサンタさん?
「みんな人が入ってやってるんだね。」「本当は誰々だよね」。
そんな、なまいきな言葉が子供たちから聞こえてきそうです。
ご家庭では、サンタをどんなふうに説明していますか?いやそれとも説明などしていませんか?
こんな時代、情報過多の時代だからこそ本物に大人が触れさせることが大事です。
大人には説明責任があるのです。本物を伝えましょう。
そしていい悪いの善悪の判断を親が責任もって示してやることが大事です。ダメなことはダメというけじめ。
冬休み、家庭にいる時間が長くなります。子供といろんなことを話す時間を創りましょう。
TVに時間を持っていかれないように、向かい合いましょう。いろいろな発見がきっとあると思いますよ。
14.脳の発達と睡眠
2010-04-07
以前、表記タイトルでNHKで特集をやっていて見た方もいると思いますが、睡眠と脳の成長は
実は深い関係にあります。
TVでやっていたように正しい3角形が画けたでしょうか?かけない子が増えています。
3角形という言葉も知らない年長児もいました。
斜めの線を引くということは、今までの経験や脳の発達とも関係しています。
話は戻りますが、お子さんを今、何時に寝せているでしょうか。夜10時とか、11時!に寝せてるようでしたら、即刻生活リズムをあらためてください。大人の時間に子供を無意識に合わせてしまいませんか?本当は子供の時間に大人が合わせるべきものです。
遅い時間に寝るとなぜ悪いかというと、子供、特に幼稚園以下の子供には成長ホルモンが夜、活発に分泌されます。これは夜寝てから約2時間かかるといわれています。 仮に10時に寝ると12時になるわけです。11時だと、、、。
朝、ぼ〜として活動に入っていけない子、先生の話に集中できない子、一人で遊んでいるときが多い子などは統計で、だいたいが夜遅いパターンの夜型の生活リズムになってしまっている子がほとんどです。
そして自立起床(自分で自然に起きること)ができませんから、いつも母親と朝の言い争いになってしまいます。「起きなさい〜」等々です。そういう子(つまり、自分で起きれない他律起床の子)は午後3時ごろになってやっと目覚めはじめますから、夜の活動が活発になって活動が明らかにずれてきます。まさしく悪循環ですね。
ではどうしたらいいでしょうか。これはズバリ、親の生活リズムを変えるしかありません。夜遅くとも9時までには寝せるためには逆算して、6時に食事を必ずするという習慣をつけるということです。そして7時にオフロに入れる、と絵本を読む時間もたっぷり作れて9時前には就寝することができます。早めにオフロに入るのもいいでしょう。
大事なことは食事の時間の用意をその前に済ませるということです。この時間が遅れるとだんだん先延ばしになってきます。「寝る子は育つ」という昔からの言い伝えは、的を得ているのです。
簡単なことですが、実はこの習慣病から抜け出すには、最初、努力が必要です。でもここから抜け出さないと、あとで大きなつけを子育てで払わないといけない羽目になります。
おどかすわけではありませんが、脳の活動はこの時期が一番活発になるからです。
今改めるか、後でするかの差は大きくなってからはっきりします。
でも一旦このリズムができて、子供を早く寝かしつけてしまうと、そこには意外に十分な大人の時間が確保できることに気がつくでしょう。
ただ、途中で昼寝をすると困ります。多少ならいいですが、時間がきたら、少しかわいそうでも強制的に起こすことが必要です。やり方でしょうが、最初、できれば昼寝をさせないでリズムを作っていくと効果があがります。
でもこの習慣ができてしまうとしめたものです。子供はその時間になると自然に眠くなります。適時に寝て朝すっきりと早めに起きる。起きるときも寒くても、思い切って「パッと」起きる。ということを毎日習慣づけていくと子供も確実に変わってきます。(朝6時から6時半の間に起きるのが理想です。)
「親のなるように、子供育つ」ということわざがあります。規則正しい生活リズムは子供にとっても親自身にとってもいいことです。やらなければ何も変わりません。ぜひ、明日から生活を少しでも変えて、リフレッシュしてみましょう。子供たちのためです。
実は深い関係にあります。
TVでやっていたように正しい3角形が画けたでしょうか?かけない子が増えています。
3角形という言葉も知らない年長児もいました。
斜めの線を引くということは、今までの経験や脳の発達とも関係しています。
話は戻りますが、お子さんを今、何時に寝せているでしょうか。夜10時とか、11時!に寝せてるようでしたら、即刻生活リズムをあらためてください。大人の時間に子供を無意識に合わせてしまいませんか?本当は子供の時間に大人が合わせるべきものです。
遅い時間に寝るとなぜ悪いかというと、子供、特に幼稚園以下の子供には成長ホルモンが夜、活発に分泌されます。これは夜寝てから約2時間かかるといわれています。 仮に10時に寝ると12時になるわけです。11時だと、、、。
朝、ぼ〜として活動に入っていけない子、先生の話に集中できない子、一人で遊んでいるときが多い子などは統計で、だいたいが夜遅いパターンの夜型の生活リズムになってしまっている子がほとんどです。
そして自立起床(自分で自然に起きること)ができませんから、いつも母親と朝の言い争いになってしまいます。「起きなさい〜」等々です。そういう子(つまり、自分で起きれない他律起床の子)は午後3時ごろになってやっと目覚めはじめますから、夜の活動が活発になって活動が明らかにずれてきます。まさしく悪循環ですね。
ではどうしたらいいでしょうか。これはズバリ、親の生活リズムを変えるしかありません。夜遅くとも9時までには寝せるためには逆算して、6時に食事を必ずするという習慣をつけるということです。そして7時にオフロに入れる、と絵本を読む時間もたっぷり作れて9時前には就寝することができます。早めにオフロに入るのもいいでしょう。
大事なことは食事の時間の用意をその前に済ませるということです。この時間が遅れるとだんだん先延ばしになってきます。「寝る子は育つ」という昔からの言い伝えは、的を得ているのです。
簡単なことですが、実はこの習慣病から抜け出すには、最初、努力が必要です。でもここから抜け出さないと、あとで大きなつけを子育てで払わないといけない羽目になります。
おどかすわけではありませんが、脳の活動はこの時期が一番活発になるからです。
今改めるか、後でするかの差は大きくなってからはっきりします。
でも一旦このリズムができて、子供を早く寝かしつけてしまうと、そこには意外に十分な大人の時間が確保できることに気がつくでしょう。
ただ、途中で昼寝をすると困ります。多少ならいいですが、時間がきたら、少しかわいそうでも強制的に起こすことが必要です。やり方でしょうが、最初、できれば昼寝をさせないでリズムを作っていくと効果があがります。
でもこの習慣ができてしまうとしめたものです。子供はその時間になると自然に眠くなります。適時に寝て朝すっきりと早めに起きる。起きるときも寒くても、思い切って「パッと」起きる。ということを毎日習慣づけていくと子供も確実に変わってきます。(朝6時から6時半の間に起きるのが理想です。)
「親のなるように、子供育つ」ということわざがあります。規則正しい生活リズムは子供にとっても親自身にとってもいいことです。やらなければ何も変わりません。ぜひ、明日から生活を少しでも変えて、リフレッシュしてみましょう。子供たちのためです。
15.幼児と睡眠 (「日本の赤ちゃんは夜更かし気味」)
2010-04-07
日本の赤ちゃんの約半数が夜10時以降に就寝。こんな結果がP&Gあかちゃん研究所の調査ででた。昨年(‘04年)12月に実施した、0ヶ月から48ヶ月(4歳)の子を持つ親が回答したデータである。なんと47%が10時以降に寝ていることがわかった。
欧州で同じ子を持つ親に聞いた同様の調査では、「午後10時以降就寝」はフランス・ドイツで16%、英国が25%、スウェーデンが27%と、日本より大幅に少なかった。
夜9時以降に赤ちゃんを商業施設に連れ出したことがあると答えたのは26%。コンビニエンスストアやレンタルビデオ店が多かったそうです。大人の生活習慣に巻き込まれて、日本は世界有数の「夜更かし赤ちゃん容認の国」で、赤ちゃんの睡眠リズムに乱れをもたらしている。先日、TVでも睡眠障害が大脳に及ぼす影響を放映していました。夜眠れない習慣がつくとどうなるか、子どもの中に有る体内ホルモンのバランスが崩れて、精神が不安定になり、他動などの原因になるということが医学的にわかってきました。こんなところに実は原因があったのです。また、それにも増して、2歳児半のテレビ視聴率が上がってきているのも気になるところです。その1割は1日4時間以上もみている実態が出ています。これでもか、これでもかというぐらい一方的な音と光の攻撃を浴びている子どもたち。子どもの精神が、どうなっていくのか非常に心配です。睡眠の減少とアンバランスな1日の生活時間、ただつけているだけのTVをBGMのようにして育っていく子どもたち。そんな家庭環境の中で育てられた子どもたち。
遊びが集中できない子、友達が作れない子、みんなと仲間に入っていけない子が増えている今、そして自分のことが自己主張できない子などが増えている今、その原因は今おこなわれている無意識な生活時間の中に実は原因があるのを実感していただきたいと思います。
大人の生活に子どもを引きずり込むのではなく、子どもには、大切な子どもの生活時間があることを早く気づいて、遅くとも9時30まではベッドに連れて行って、正しいリズムをつけることが生育期には最も重要なことを身に染みて理解していただきたいと思います。
欧州で同じ子を持つ親に聞いた同様の調査では、「午後10時以降就寝」はフランス・ドイツで16%、英国が25%、スウェーデンが27%と、日本より大幅に少なかった。
夜9時以降に赤ちゃんを商業施設に連れ出したことがあると答えたのは26%。コンビニエンスストアやレンタルビデオ店が多かったそうです。大人の生活習慣に巻き込まれて、日本は世界有数の「夜更かし赤ちゃん容認の国」で、赤ちゃんの睡眠リズムに乱れをもたらしている。先日、TVでも睡眠障害が大脳に及ぼす影響を放映していました。夜眠れない習慣がつくとどうなるか、子どもの中に有る体内ホルモンのバランスが崩れて、精神が不安定になり、他動などの原因になるということが医学的にわかってきました。こんなところに実は原因があったのです。また、それにも増して、2歳児半のテレビ視聴率が上がってきているのも気になるところです。その1割は1日4時間以上もみている実態が出ています。これでもか、これでもかというぐらい一方的な音と光の攻撃を浴びている子どもたち。子どもの精神が、どうなっていくのか非常に心配です。睡眠の減少とアンバランスな1日の生活時間、ただつけているだけのTVをBGMのようにして育っていく子どもたち。そんな家庭環境の中で育てられた子どもたち。
遊びが集中できない子、友達が作れない子、みんなと仲間に入っていけない子が増えている今、そして自分のことが自己主張できない子などが増えている今、その原因は今おこなわれている無意識な生活時間の中に実は原因があるのを実感していただきたいと思います。
大人の生活に子どもを引きずり込むのではなく、子どもには、大切な子どもの生活時間があることを早く気づいて、遅くとも9時30まではベッドに連れて行って、正しいリズムをつけることが生育期には最も重要なことを身に染みて理解していただきたいと思います。
16.キレない子 (3才までの愛情 大事)
2010-04-07
先ごろ朝日新聞に表記のような題材で記事がありました。文部科学省の検討会の内容で(座長 有馬朗人元文相)、述べているのは結論的に言うと「キレる子」にしないためには乳幼児期の家族の愛情や生活リズムが大切だとする内容です。
人間の情動(感情の動き)は5歳ごろまでにその原型が作られるとし、「取り返しは不可能ではないが、年齢とともに困難になる。つまり3才ごろまでに母親の愛情や、家族の愛情を受けるのが望ましい。」と述べています。脳内コミニュケーションや意欲をつかさどる「前頭連合野」の発達は8歳頃までがピークで、二十歳ごろまで続くとも述べられています。
当たり前のことですが改めて聞くとギクッとする方も多いのではないでしょうか。つまり、幼児期の家庭での愛情がいかに大事であるか分かると思います。その後のその子(その人間)の一生を左右するほど大事な時期でもある改めていえます。心理学でいうと、この時期「感覚感情期」は無意識の領域でもありますから、ここで述べているように年齢が重ねられるほど、修正は困難になります。
昨今、世の中で親としての未発達さと、あるいは子どもの未発達さゆえの痛ましい事件が繰り返し行われていますが、以前にもここで述べたようにTVやビデオゲームの影響もさることながら、すぐキレルとか、衝動的になるなど問題のある子は基本的には、その幼少期の家庭での育てられ方にあると言い切れます。この基本の時期、建物で言えば土台、その基礎がとても大事だと結論付けられているわけです。そんな大事な時期であるこの乳幼児期、親が親として、自分の子に対して、どう関わっていったらよいか。子育てのこの最高の時期、時間を親としてどう関わるか、あらためて子育ての「意義」、「親」であることの意義も問われているといえるでしょう。
人間の情動(感情の動き)は5歳ごろまでにその原型が作られるとし、「取り返しは不可能ではないが、年齢とともに困難になる。つまり3才ごろまでに母親の愛情や、家族の愛情を受けるのが望ましい。」と述べています。脳内コミニュケーションや意欲をつかさどる「前頭連合野」の発達は8歳頃までがピークで、二十歳ごろまで続くとも述べられています。
当たり前のことですが改めて聞くとギクッとする方も多いのではないでしょうか。つまり、幼児期の家庭での愛情がいかに大事であるか分かると思います。その後のその子(その人間)の一生を左右するほど大事な時期でもある改めていえます。心理学でいうと、この時期「感覚感情期」は無意識の領域でもありますから、ここで述べているように年齢が重ねられるほど、修正は困難になります。
昨今、世の中で親としての未発達さと、あるいは子どもの未発達さゆえの痛ましい事件が繰り返し行われていますが、以前にもここで述べたようにTVやビデオゲームの影響もさることながら、すぐキレルとか、衝動的になるなど問題のある子は基本的には、その幼少期の家庭での育てられ方にあると言い切れます。この基本の時期、建物で言えば土台、その基礎がとても大事だと結論付けられているわけです。そんな大事な時期であるこの乳幼児期、親が親として、自分の子に対して、どう関わっていったらよいか。子育てのこの最高の時期、時間を親としてどう関わるか、あらためて子育ての「意義」、「親」であることの意義も問われているといえるでしょう。
17.ディスプレイ文化の進行
2010-04-07
前回(VOL.11)にてTVの弊害や早寝早起きの大切さをお話しましたが、新聞によると、遅く寝ている子、夜10時以降に起きている子は何をしているかというと、そのほとんどはテレビやビデオの視聴です。その原因は子供が大人の生活習慣と同じになっていることです。そして、子供の食事の様子で気に掛かっていることの7割近くが「テレビを見ながら食事をすること」です。だったら切ればいいことですが、TVがBGMのように生活に当たり前のようになっている状態では、ことに難しさもあります。
実際に幼児期の子供がTVを見ている時間は、平均2時間12分と言われています。世界で一番テレビを見る民族です。次はビデオですが、例えば2歳児のビデオ利用は幼児番組の少ない時間帯で利用されることが多いというのです。ということはTVの幼児番組が終わるとすぐさまビデオを見ていることを表しています。こういったように日本の子どもはいつでもテレビを見られる状態が当然だと思っているので、我慢することがしだいに苦手になってきます。それとTVゲームやパソコンの進行。最近は低学年でも使える子が出てきています。これらメディアを総称してディスプレイ文化の進行といいます。
ショッキングなことにアメリカの小児学会の報告ですが、乳幼児期にテレビを多く見た子ほど、就学してから集中力が弱い、落ち着きがない、衝動的な行動をとりやすい危険性が増えてくることが報告されています。日本の小児学会でもTVやビデオを見ている子どもは、そうでない子どもに比べて言葉の発達の遅れがあると報告されています。
こういったTVやビデオの視聴にたくさんの時間を費やすので、親との絆も少しずつ希薄になってきているのではないかと思います。つまり、未熟な「個」の出来上がりです。こんな状態がジワジワ蓄積されて、落ち着きのない子ども、切れやすい子どもが乱造されているとしたらどうでしょうか。この子達が大人になったらと・・考えるのは私だけでしょうか。
そこで様々なメディアに対して、5つの提案を参考までにここで紹介します。
? 授乳中や食事中のTVは極力控える!消す!
? TVやビデオの視聴は一日2時間までとする。それより、人と関わる戸外の遊びをしてその楽しさを体験させる。
? TVは見る時間を決める。番組を決める。
? 見終わったら消す!(ここが大事です)
? TVを見せるときは、親も一緒に見る。・・会話をしながら見る。・・です。
家庭でTVやメディアに対して話し合い、ルールなどを作って少しでも今の状況を一変することが必要なのではないでしょうか。TVの奴隷になっていませんか?
実際に幼児期の子供がTVを見ている時間は、平均2時間12分と言われています。世界で一番テレビを見る民族です。次はビデオですが、例えば2歳児のビデオ利用は幼児番組の少ない時間帯で利用されることが多いというのです。ということはTVの幼児番組が終わるとすぐさまビデオを見ていることを表しています。こういったように日本の子どもはいつでもテレビを見られる状態が当然だと思っているので、我慢することがしだいに苦手になってきます。それとTVゲームやパソコンの進行。最近は低学年でも使える子が出てきています。これらメディアを総称してディスプレイ文化の進行といいます。
ショッキングなことにアメリカの小児学会の報告ですが、乳幼児期にテレビを多く見た子ほど、就学してから集中力が弱い、落ち着きがない、衝動的な行動をとりやすい危険性が増えてくることが報告されています。日本の小児学会でもTVやビデオを見ている子どもは、そうでない子どもに比べて言葉の発達の遅れがあると報告されています。
こういったTVやビデオの視聴にたくさんの時間を費やすので、親との絆も少しずつ希薄になってきているのではないかと思います。つまり、未熟な「個」の出来上がりです。こんな状態がジワジワ蓄積されて、落ち着きのない子ども、切れやすい子どもが乱造されているとしたらどうでしょうか。この子達が大人になったらと・・考えるのは私だけでしょうか。
そこで様々なメディアに対して、5つの提案を参考までにここで紹介します。
? 授乳中や食事中のTVは極力控える!消す!
? TVやビデオの視聴は一日2時間までとする。それより、人と関わる戸外の遊びをしてその楽しさを体験させる。
? TVは見る時間を決める。番組を決める。
? 見終わったら消す!(ここが大事です)
? TVを見せるときは、親も一緒に見る。・・会話をしながら見る。・・です。
家庭でTVやメディアに対して話し合い、ルールなどを作って少しでも今の状況を一変することが必要なのではないでしょうか。TVの奴隷になっていませんか?