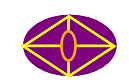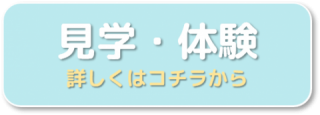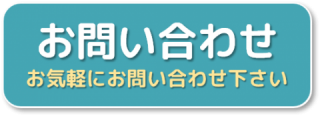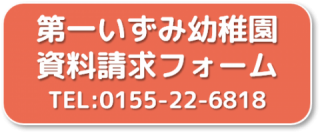園長通信
園長先生からのメッセージ
3.「しつけについて」
2010-04-07
しつけについて再びお話させていただきます。
しつけとはある意味その子にどう育ってほしいのか、何を身につけてほしいのか、その子が自主的に、自発的に自分の意志で動けるようにようになるにはどうしたらよいかを教えていく事でもあります。
つまり、期待する行動が習慣となって自然に出来るようになる事なのです。
しつけは時代時代の文化や背景によって変わってくるものですが、内容は変わってもその基本的なものの考え方は今も変わりません。
しつけというと、洋服を一人で脱いだり着たり、トイレに一人でいけるようになることなど、いわゆる基本的生活習慣の自立を思い描く人が多いと思われます。何でも一人ですることが自立した子だと思われますが、本当に自立した行動ができる人というのは、人との調和で何かが出来る人、つまり人を信じることのできる人です。
親子の場合は、親との人間関係がしっかり作れていることが大切です。
無条件で受け入れる。子供は自分が本当に愛されていることを知ると、その信頼感から他の人に対しても信頼できるようになり、自分自身も信じはじめて本当の自信をもつということができるのです。
安心して親の手を借りればいいということを伝えるだけで、他の人の手も借りられ、また自分が手を貸してあげられるようになります。決して子供の要求をを叶えすぎることがわがままや自立の遅い子にならないわけです。それを見極める親の目も大切ですが、それ以上に人に頼ること、人から頼られる事。この2つのバランスをよく育ててあげる事が大切です。
それともう一つ大切なことは、「家庭がやすらげる場」であることが、基本的に、根本的に一番大切な大条件であるということです。
しつけの5つのポイント
ではしつけの心構えについて5つだけのポイントにしぼってまとめてみました。
1.根気強くわかるように教える
親がつい感情的になって「何度言ったらわかるの!」とおどしても子供には伝わりません。
前の事を持ち出すのも禁物です。わかりやすく何度でも繰り返す事が一番の近道です。
ここは「がまん」です。
2.お手本を示してあげる
幼児心理の特徴の1つが”具体性”ということです。自分の目や耳で実際に見たり聞いたりしたことしか 理解できないのです。「おはよう」「こんにちは」といったあいさつが出来る子になってほしいと思っているなら、その人自身が、いつも周囲に気持ちよくすがすがしいあいさつをしているかどうかです。子は親の鏡です。
親が身をもって示す事が一番伝わります。
3.例外はなるべく認めない
寝る前の歯磨きなどきちんとつけさせたい習慣ですが,今日は眠たがっているからとか遅いから今晩だけは特別、ということになれば次の夜も、その次もということになってしまいます。せっかくやっていた事が意味のないものになってしまいます。先に話した”根気”は大切です。
親がいつも一貫した態度で臨みましょう。歯を磨かなければ気持ちが悪くて眠れないという習慣がつけばしめたものです。
4.認めて、誉めてあげる
簡単なことですが、なかなかできないことの一つではないでしょうか。親や先生から誉められ、認められるのは子供にとって大変快いことですが、大人はあまりそれを理解していません。
お片づけを「上手になったね」などと楽しい気持ちを持たせることが大切です。
5.長い目でしつけをとらえる
現代は情報が過多で選択が難しくなってきています。それと目先のことだけに親はとらわれがちになってきています。トイレがうまくいかない、片づけが出来ないなど…しかし、こどもには心と体にそれぞれ発達段階があります。
乳幼児期には特にお母さんとの基本的信頼感が必要で、それが全てのベースになって、周囲との人間関係を身に付け自立していきます。今出来ない事もあせらずゆったりとした構えで向かい合う事が大切です。
必ず出来るようになります。しかし長い目といっても”つ”がつく年令(9つ)までの間にしておいてください。
それ以降は難しくなります。
この5つはいずれもしつけのポイントだけをわかりやすくまとめたものです。
しつけに悩んでいるならこの5つの点を常に頭にいれてお子さんに接してください。ここをやり続けると必ずお子さんの行動が変わります。
しつけはあせらずポイントを抑えて一歩一歩の道のりです。
しつけとはある意味その子にどう育ってほしいのか、何を身につけてほしいのか、その子が自主的に、自発的に自分の意志で動けるようにようになるにはどうしたらよいかを教えていく事でもあります。
つまり、期待する行動が習慣となって自然に出来るようになる事なのです。
しつけは時代時代の文化や背景によって変わってくるものですが、内容は変わってもその基本的なものの考え方は今も変わりません。
しつけというと、洋服を一人で脱いだり着たり、トイレに一人でいけるようになることなど、いわゆる基本的生活習慣の自立を思い描く人が多いと思われます。何でも一人ですることが自立した子だと思われますが、本当に自立した行動ができる人というのは、人との調和で何かが出来る人、つまり人を信じることのできる人です。
親子の場合は、親との人間関係がしっかり作れていることが大切です。
無条件で受け入れる。子供は自分が本当に愛されていることを知ると、その信頼感から他の人に対しても信頼できるようになり、自分自身も信じはじめて本当の自信をもつということができるのです。
安心して親の手を借りればいいということを伝えるだけで、他の人の手も借りられ、また自分が手を貸してあげられるようになります。決して子供の要求をを叶えすぎることがわがままや自立の遅い子にならないわけです。それを見極める親の目も大切ですが、それ以上に人に頼ること、人から頼られる事。この2つのバランスをよく育ててあげる事が大切です。
それともう一つ大切なことは、「家庭がやすらげる場」であることが、基本的に、根本的に一番大切な大条件であるということです。
しつけの5つのポイント
ではしつけの心構えについて5つだけのポイントにしぼってまとめてみました。
1.根気強くわかるように教える
親がつい感情的になって「何度言ったらわかるの!」とおどしても子供には伝わりません。
前の事を持ち出すのも禁物です。わかりやすく何度でも繰り返す事が一番の近道です。
ここは「がまん」です。
2.お手本を示してあげる
幼児心理の特徴の1つが”具体性”ということです。自分の目や耳で実際に見たり聞いたりしたことしか 理解できないのです。「おはよう」「こんにちは」といったあいさつが出来る子になってほしいと思っているなら、その人自身が、いつも周囲に気持ちよくすがすがしいあいさつをしているかどうかです。子は親の鏡です。
親が身をもって示す事が一番伝わります。
3.例外はなるべく認めない
寝る前の歯磨きなどきちんとつけさせたい習慣ですが,今日は眠たがっているからとか遅いから今晩だけは特別、ということになれば次の夜も、その次もということになってしまいます。せっかくやっていた事が意味のないものになってしまいます。先に話した”根気”は大切です。
親がいつも一貫した態度で臨みましょう。歯を磨かなければ気持ちが悪くて眠れないという習慣がつけばしめたものです。
4.認めて、誉めてあげる
簡単なことですが、なかなかできないことの一つではないでしょうか。親や先生から誉められ、認められるのは子供にとって大変快いことですが、大人はあまりそれを理解していません。
お片づけを「上手になったね」などと楽しい気持ちを持たせることが大切です。
5.長い目でしつけをとらえる
現代は情報が過多で選択が難しくなってきています。それと目先のことだけに親はとらわれがちになってきています。トイレがうまくいかない、片づけが出来ないなど…しかし、こどもには心と体にそれぞれ発達段階があります。
乳幼児期には特にお母さんとの基本的信頼感が必要で、それが全てのベースになって、周囲との人間関係を身に付け自立していきます。今出来ない事もあせらずゆったりとした構えで向かい合う事が大切です。
必ず出来るようになります。しかし長い目といっても”つ”がつく年令(9つ)までの間にしておいてください。
それ以降は難しくなります。
この5つはいずれもしつけのポイントだけをわかりやすくまとめたものです。
しつけに悩んでいるならこの5つの点を常に頭にいれてお子さんに接してください。ここをやり続けると必ずお子さんの行動が変わります。
しつけはあせらずポイントを抑えて一歩一歩の道のりです。
4.卒園式の練習に見る年長の顔
2010-04-07
卒園式の練習をしていると、つくづく年長児の顔つきが変わったなと感じます。神妙な面持ちで手にする証書。みんな少しづつ近づいてくるその日に対して、ことの重大さを感じているような気がします。
去年の5月ごろ、1学期ではまだまだ、年中組かなと思うくらいでしたが、運動会が過ぎたころから変わってきて、2学期にはもう本物の年長組になっていました。そして今は、もう小学生の顔つきです。
自分で判断したり、考えたり、少しぐらい厳しくてもガンバル忍耐力もつけてきました。教師にとっても、今までの苦労が実る充実期の3学期です。もっといろんな事をさせたい、協力してこんなこともできる、等々ありますが、あと数日で幼稚園ともお別れとなるのは、なんとも離しがたい、さびしい気持ちになってしまいます。担任ならこの想いはなお更のことでしょう。願わくば、小学校でリーダーシップを発揮して、より羽ばたいてほしいと思うばかりです。
小学校の1年生はまだまだ幼稚園の延長と考えるふしもありますが、決してそうではありません。彼らは自分で解決する力、友と一緒に考え、協力する力、見通しを持った遊びや仕事の姿勢などたくさんの力をもっています。大人が思っている以上の能力を持っているのです。偏見がその能力を摘んでしまっているのです。
親も小学校もどうか、1年生を過小評価しないでいただきたい。少なくとも帯西幼稚園で学んだ子は違うはずです。自己満足に聞こえるかもしれませんがそういう姿勢で教育しているのです。集団生活での学びはこれから益々重要になっていくでしょう。家庭で教えることには時代が限界に来ているような気がしないでもありません。子供の顔つきが変わってきているの見られるのは学校など集団生活の場だけでしょう。そこがやりどきなのです。
証書の受け渡しの練習をしている彼らの顔に緊張とその影に自信が見えて頼もしくみえます。
当日は立派な卒園式をやってくれるでしょう。ガンバレ帯西っ子。
去年の5月ごろ、1学期ではまだまだ、年中組かなと思うくらいでしたが、運動会が過ぎたころから変わってきて、2学期にはもう本物の年長組になっていました。そして今は、もう小学生の顔つきです。
自分で判断したり、考えたり、少しぐらい厳しくてもガンバル忍耐力もつけてきました。教師にとっても、今までの苦労が実る充実期の3学期です。もっといろんな事をさせたい、協力してこんなこともできる、等々ありますが、あと数日で幼稚園ともお別れとなるのは、なんとも離しがたい、さびしい気持ちになってしまいます。担任ならこの想いはなお更のことでしょう。願わくば、小学校でリーダーシップを発揮して、より羽ばたいてほしいと思うばかりです。
小学校の1年生はまだまだ幼稚園の延長と考えるふしもありますが、決してそうではありません。彼らは自分で解決する力、友と一緒に考え、協力する力、見通しを持った遊びや仕事の姿勢などたくさんの力をもっています。大人が思っている以上の能力を持っているのです。偏見がその能力を摘んでしまっているのです。
親も小学校もどうか、1年生を過小評価しないでいただきたい。少なくとも帯西幼稚園で学んだ子は違うはずです。自己満足に聞こえるかもしれませんがそういう姿勢で教育しているのです。集団生活での学びはこれから益々重要になっていくでしょう。家庭で教えることには時代が限界に来ているような気がしないでもありません。子供の顔つきが変わってきているの見られるのは学校など集団生活の場だけでしょう。そこがやりどきなのです。
証書の受け渡しの練習をしている彼らの顔に緊張とその影に自信が見えて頼もしくみえます。
当日は立派な卒園式をやってくれるでしょう。ガンバレ帯西っ子。
5.根気と集中力のある子を育てる
2010-04-07
しばらく、園長通信がなかったので、長らくご父兄の皆様に失礼致しました。書く時間が忙しくてなかったと言うと言い訳になりますが、いろんな声も頂いていますので今後少しづつでも継続していこうと肝に銘じております。お許し下さい。
最近思っていることを少しづつでも、勝手に書き連ねていこうと思います。 教育のひとつの姿として「好きなものを、
好きなときに、好きなようにやらせる」いわゆる、自主尊重の子ども中心主義というのがあります。
「勉強は、自分が意欲がわいたときにすればいい。」などという人がいますが、子どもは放っておけばいつまでたっても
勉強しないし、遅れていきます。これはいかにも子どもを大事に育てているようで聞こえはいいのですが確実に子どもをだめにしてしまいます。
教育の基本は「生きる力を育てること」にあるのです。生きる力とは、様々な困難を自ら克服する能力です。
そのためには「やり抜く力」を身につけさせなければなりません。
「やる気」というのは、束縛を強いられるようなとき初めておこるものです。 それなのに、今飽食の日本で「好きなことを、好きなときに、好きなようにやってもいいよ」と、常に欲求が満たされた状態ではどうでしょうか?活力は間違いなく生まれません。子どもに限った話ではないかとも思います。
欲求を制限する社会のルールがなくなったとき、精神がくずれるといいます。そんなひずみが社会のあちこちで起きているのは承知のことと思います。 ではやる気を起こすにはどうしたらよいか、これはまず、やってみたいという動機付けとその思いを爆発させることのできる環境にあるといいます。
そしてもうひとつ、その方向に自分を向けていく自己統制力です。羅針盤です。
まず環境から、すべきことは生活習慣の見直しです。早寝、早起きを徹底し、三度の食事をきっちり取らせる。規律を家庭内に作って生活のリズムを整えること、これが基本です。緩んだ環境からは、活力は生まれません。ただし子供にだけ求めてもダメです。親の怠惰な生活を変えないで子供に意欲を出せといっても無理な話です。まず親自身が生活を見つめ直し家庭の緩みを引き締めることです。
やる気の方向性はその価値観です。毎日を振り返ることです。他人の目に自分はどう映ったか、他人の言葉にどう感じたのか、繰り返し反省してみる。このことを習慣化させることが自己を整えていくと言われています。親は絶えず子供に問い掛けて反省を促し、自分で考えさせる。結論をすぐに教えず、考えさせる。これは親の姿勢も問われるということです。
子育てに明快な答えがあるわけではありませんが、絶えず毎日を振り返り工夫していく、毎日の地道な積み重ねが大切であるといいうことです。子育ては自分育て、親子での長い修行です。一歩一歩対話を増やして親が人としてあるべき方向を示してやる。難しいことですが今、問われているのは一番子供との時間を共有している親であるということです。結局親の姿を一番参考にして学習しているのですから。
この生活習慣の見直しと日々の反省、そして子供への問いかけが大切です。
親も好き勝手なことをしていてはだめです。ひとつでも我慢をしていく、その緊張感が家庭の雰囲気を変えます。強い精神はそんな親の姿を見て育ちます。 強い人間に育てるために、子どもにやり抜く、我慢できる、強い心を身に付けさせましょう。
最近思っていることを少しづつでも、勝手に書き連ねていこうと思います。 教育のひとつの姿として「好きなものを、
好きなときに、好きなようにやらせる」いわゆる、自主尊重の子ども中心主義というのがあります。
「勉強は、自分が意欲がわいたときにすればいい。」などという人がいますが、子どもは放っておけばいつまでたっても
勉強しないし、遅れていきます。これはいかにも子どもを大事に育てているようで聞こえはいいのですが確実に子どもをだめにしてしまいます。
教育の基本は「生きる力を育てること」にあるのです。生きる力とは、様々な困難を自ら克服する能力です。
そのためには「やり抜く力」を身につけさせなければなりません。
「やる気」というのは、束縛を強いられるようなとき初めておこるものです。 それなのに、今飽食の日本で「好きなことを、好きなときに、好きなようにやってもいいよ」と、常に欲求が満たされた状態ではどうでしょうか?活力は間違いなく生まれません。子どもに限った話ではないかとも思います。
欲求を制限する社会のルールがなくなったとき、精神がくずれるといいます。そんなひずみが社会のあちこちで起きているのは承知のことと思います。 ではやる気を起こすにはどうしたらよいか、これはまず、やってみたいという動機付けとその思いを爆発させることのできる環境にあるといいます。
そしてもうひとつ、その方向に自分を向けていく自己統制力です。羅針盤です。
まず環境から、すべきことは生活習慣の見直しです。早寝、早起きを徹底し、三度の食事をきっちり取らせる。規律を家庭内に作って生活のリズムを整えること、これが基本です。緩んだ環境からは、活力は生まれません。ただし子供にだけ求めてもダメです。親の怠惰な生活を変えないで子供に意欲を出せといっても無理な話です。まず親自身が生活を見つめ直し家庭の緩みを引き締めることです。
やる気の方向性はその価値観です。毎日を振り返ることです。他人の目に自分はどう映ったか、他人の言葉にどう感じたのか、繰り返し反省してみる。このことを習慣化させることが自己を整えていくと言われています。親は絶えず子供に問い掛けて反省を促し、自分で考えさせる。結論をすぐに教えず、考えさせる。これは親の姿勢も問われるということです。
子育てに明快な答えがあるわけではありませんが、絶えず毎日を振り返り工夫していく、毎日の地道な積み重ねが大切であるといいうことです。子育ては自分育て、親子での長い修行です。一歩一歩対話を増やして親が人としてあるべき方向を示してやる。難しいことですが今、問われているのは一番子供との時間を共有している親であるということです。結局親の姿を一番参考にして学習しているのですから。
この生活習慣の見直しと日々の反省、そして子供への問いかけが大切です。
親も好き勝手なことをしていてはだめです。ひとつでも我慢をしていく、その緊張感が家庭の雰囲気を変えます。強い精神はそんな親の姿を見て育ちます。 強い人間に育てるために、子どもにやり抜く、我慢できる、強い心を身に付けさせましょう。
6.誉めること、叱ること
2010-04-07
最近バートランド・ラッセル(1872〜1970)という人の教育論の「幼児の教育について」の中に「誉めること、叱ること」についてこんな一節があったので、非常に共感してしまいましたのでご紹介します。
「誉めること、叱ること」もしないで教育を行うことは不可能だと私は信じている。けれどもこの二つのものについてはある程度の用心が必要である。
第一に、この二つとも他の子供との比較を示すものであってはならない。
第二に、叱ることは、誉めることよりもずっと控えめにしなければならない。
第三に、誉めることは、当たり前のことに対しては与えられてはならない。
注)三つとも意味深い言葉です。二つ目は特に親として、三つ目は特に我々教師も注意しなければならない言葉です。ともすると、何かができるとつい当たり前のようになんでもかんでも誉めてしまいがちですが、いかがでしょうか?実はその範囲が大切なのです。
親はけっして子供に媚びてはいけません。子供の機嫌を伺うなど、もってのほかです。親はよき人生の指導者でなければならないのです。大事なことを見極めてしっかり誉めてやるのです。そのTPOにわけて大事なところで誉める、大事なところで叱る。むやみに誉めたり、叱ったりすることがいかにその言葉を無為な物にしているか、効力をなくしたものとしているか私たちは考え直さないといけないでしょう。
この言葉に深くうなずいてしまいました。再考ください。
「誉めること、叱ること」もしないで教育を行うことは不可能だと私は信じている。けれどもこの二つのものについてはある程度の用心が必要である。
第一に、この二つとも他の子供との比較を示すものであってはならない。
第二に、叱ることは、誉めることよりもずっと控えめにしなければならない。
第三に、誉めることは、当たり前のことに対しては与えられてはならない。
注)三つとも意味深い言葉です。二つ目は特に親として、三つ目は特に我々教師も注意しなければならない言葉です。ともすると、何かができるとつい当たり前のようになんでもかんでも誉めてしまいがちですが、いかがでしょうか?実はその範囲が大切なのです。
親はけっして子供に媚びてはいけません。子供の機嫌を伺うなど、もってのほかです。親はよき人生の指導者でなければならないのです。大事なことを見極めてしっかり誉めてやるのです。そのTPOにわけて大事なところで誉める、大事なところで叱る。むやみに誉めたり、叱ったりすることがいかにその言葉を無為な物にしているか、効力をなくしたものとしているか私たちは考え直さないといけないでしょう。
この言葉に深くうなずいてしまいました。再考ください。
7.お店屋さんごっこに見る子供たちの活動
2010-04-07
お店屋さんごっこがいよいよ近づいてきました。
子供たちはみんなお店の製作におおわらわです。自分でケーキとかお花とかおもちゃとか、みんな楽しそうに作っています。
きっと頭の中でいろんなイメージを作っているのでしょう。
今度の7日がとても楽しみのようです。
「こんなの作ったの!すごいでしょ。」とか「本物もみたいでしょ」「あれ買いに行くんだ」などと興味を膨らましている声がします。
お店屋さんごっこは帯西幼稚園がずいぶん前からやっている年中行事です。
目的は異年齢交流を興味を持って進めることです。
年長さんが年少さんのクラスに行ったり、年中さんのクラスに行ったりして一緒に製作をして準備をするのです。年長さんはびっくりするぐらいとってもお兄さん、お姉さんになっていろいろお手伝いしてくれます。
それを年中や年少さんは一種尊敬の目で見つめています。そしてお話をしながら一緒に作っています。きっとお兄さん、お姉さんの役割を肌で感じているのでしょう。そして、今度は年長さんがしてくれたように自分がやってくれることでしょうね。
とてもほほえましい交流もたくさんあります。兄弟が少なくなり、又自分の兄弟しか遊ばなくなってしまった社会構造のなかでは、とても大切な交流だと思っています。
「いらっしゃい!いらっしゃい!」というたくさんの声が聞こえてきそうです。きっと楽しいお店屋さんがたくさんできることでしょう。
写真やH.Pなどで又紹介していきます。
子供たちはみんなお店の製作におおわらわです。自分でケーキとかお花とかおもちゃとか、みんな楽しそうに作っています。
きっと頭の中でいろんなイメージを作っているのでしょう。
今度の7日がとても楽しみのようです。
「こんなの作ったの!すごいでしょ。」とか「本物もみたいでしょ」「あれ買いに行くんだ」などと興味を膨らましている声がします。
お店屋さんごっこは帯西幼稚園がずいぶん前からやっている年中行事です。
目的は異年齢交流を興味を持って進めることです。
年長さんが年少さんのクラスに行ったり、年中さんのクラスに行ったりして一緒に製作をして準備をするのです。年長さんはびっくりするぐらいとってもお兄さん、お姉さんになっていろいろお手伝いしてくれます。
それを年中や年少さんは一種尊敬の目で見つめています。そしてお話をしながら一緒に作っています。きっとお兄さん、お姉さんの役割を肌で感じているのでしょう。そして、今度は年長さんがしてくれたように自分がやってくれることでしょうね。
とてもほほえましい交流もたくさんあります。兄弟が少なくなり、又自分の兄弟しか遊ばなくなってしまった社会構造のなかでは、とても大切な交流だと思っています。
「いらっしゃい!いらっしゃい!」というたくさんの声が聞こえてきそうです。きっと楽しいお店屋さんがたくさんできることでしょう。
写真やH.Pなどで又紹介していきます。